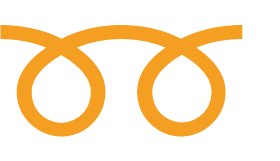2017年06月23日
【第13弾】ものづくり+α

大手企業神話‥‥‥
製造業を中心とした多くの中小企業は、
「大手企業に入り込めれば大丈夫‥‥」
「そうすれば、売上・利益が安定的に確保でき、
会社は安泰‥‥」
‥‥このような思惑で今日まで歩んできました。
まだ一部、大手企業神話は残っているにせよ、大手家電メーカーの衰退も含め神話崩壊は加速をしています。
そのような中小企業は、今まで親企業のリクエストに応じて、製品スペックを実現する為、自前の技術を磨き、製品開発をしてきました。
その自前主義での開発が他社との差別化を生み、存在価値を上げてきたのです。
この構造は何も対大手企業‥‥‥‥という事だけでは無く、受注生産型の中小零細企業に多く見受けられます。
しかし‥‥‥‥‥神話崩壊の今、顧客からのリクエストは少なくなり、市場の冷え込みに加え、スペック改善を重ねる一方で、買い替え需要はドンドン低下をしていく‥‥‥自身で首を絞める結果となり、浮上の糸口が見えない‥‥このような中小企業は多く存在しています。
それを打破するには事業開発や企業改革が必要です。
今までは、顧客のリクエストに応じる受動型、製品開発は手前主義‥‥‥‥‥‥こういう事でした。
これからの事業開発は、主体的、共創的でなければなりません。
仕掛けは能動的に‥‥事業開発は共創型で‥‥‥今までとは間逆、180度違う視点、考え方を持って臨まねばならないのです。
経済のグローバル化による競争激化により、大手企業も生き残りを掛け、様々な仕掛けをする中で、従来のネットワークの枠組みを重視する事も希薄になってきています。
そのような激変するスピードにおいて、受け身型、手前主義に拘っていては、当然ながら変化のスピードについて行けず、競争から取り残されてしまうリスクが高くなります。
強みを持つ分野に経営資源を集中し、足らざる部分は外部との連携によって補う事で、事業改革や企業改革を加速させる必要があるのです。
いわゆる「オープンイノベーション」と言われるものです。
産学連携‥‥という言葉は聞いた事があると思います。
大学と連携し、技術やアイデアを集める‥‥‥昨今、大学側も積極的に乗り出しています。
大学だけでは無く、他社との連携‥‥‥昨今では、ライバル会社と連携をして相乗効果を生み出す‥‥‥‥‥このような事も盛んになってきました。
また、資金に関しましても、クラウドで調達をする‥‥‥‥という手法もあります。
言わば、事業開発や企業改革を進める場合、余りにも早い時代の変化に対応をする為‥‥投資を極力避ける為‥‥‥‥自社には無い経営資源「人」「もの(技術)」「資金」「情報」を活用して、連携企業との相乗効果を図り開発や改革を推し進めていくという方法です。
特に、経営資源に限りがある中小企業においては有効です。
そしてそれを推し進める場合、社長自ら主体的な活動をしなければ構築は出来ません。
先般、経済産業省から毎年恒例の「ものづくり白書」が出版されました。
一様に現状における製造業の課題が露呈されています。
一方で、課題解決として『ものづくり+アルファ』という動きが、製造業において活発化し、そのような企業は増収増益傾向にあるとされています。
① 顧客の課題解決を行う「ソリューション」
②「モノの所有」から「機能の利用」「体験の提供」へ
③「顧客視点」且つ「全体最適化」
④俊敏且つ効率経営と価値最大化の仕組み
⑤オープンイノベーション活用
ものづくりを中心として、上記のような視点に着目をし、取り組まれている「ものづくり+アルファ」‥‥‥‥これらが、これからの日本のものづくりであり、中小企業の製造業が進むべき道だと考えます。
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2017/
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2017/honbun_pdf/pdf/honbun01_01_03.pdf
最新の記事
-
2022年09月06日
Vol.6 ディスプレイ広告 -
2022年08月19日
コラムVOL.5 インターネット広告の形式 -
2022年07月27日
コラムVOL.4 WEBマーケティングの集客施策【広告】 -
2022年07月15日
VOL.3 WEBマーケティングの集客施策【広報】 -
2022年06月21日
VOL.2 WEBマーケティングの集客施策 【コンテンツ】 -
2022年06月16日
VOL1.WEBマーケティングを行う理由。 -
2022年05月24日
販促キャンペーンの効果的な方法とは vol.3 -
2022年05月11日
販促キャンペーンの効果的な方法とは vol.2 -
2022年04月27日
販促キャンペーンの効果的な方法とは vol.1 -
2022年04月14日
プロモーション戦略「3C分析」から「5C分析」へ -
2022年03月09日
★2分コラム★ プロモーション戦略でよく耳にする“4P”って?? -
2022年02月26日
紫外線対策は1年中!【UV対策アイテム】を活用しよう -
2022年02月24日
【結婚式場・レストラン・ブライダルジュエリー業界向け】 -
2022年02月09日
大注目の【グラシン紙】ってなに?? -
2022年01月12日
雪や少し先の梅雨の時期【必須】ウォッシャブルアイテム -
2021年12月22日
アウトドアの季節におすすめ!マイカトラリーを持って出かけよう!! -
2021年12月08日
入社式におすすめのノベルティ -
2021年11月24日
海外で人気のグリーティングカードを贈ってみよう! -
2021年11月10日
【塾・予備校・学校向け】ノベルティで受験生を応援しよう! -
2021年10月27日
年末年始のご挨拶やイベントに!
年月アーカイブ
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (3)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (7)
- 2021年4月 (7)
- 2021年3月 (7)
- 2021年2月 (7)
- 2021年1月 (11)
- 2020年12月 (10)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (4)
- 2020年3月 (2)
- 2019年12月 (5)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (5)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (3)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (5)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)

 各種資料ダウンロード
各種資料ダウンロード
 お問い合わせ・無料相談
お問い合わせ・無料相談