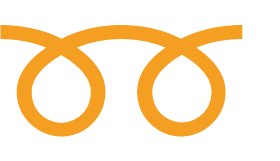2017年07月14日
【第16弾】中小製造業の生き残り策

一体、日本における中小製造業は何社位あるのでしょう?
‥‥‥‥‥答えの前に、日本の全体企業像を抑えておきましょう。
国税庁調べによりますと、全企業数は412万8215社です。
その内、法人企業は約170万社‥‥その他は個人事業主及びペーパーカンパニーで約242万社あります。
また、大手企業と中小企業の内訳は以下の通りです。
大手企業‥‥‥‥約40万社
中小企業‥‥‥‥約370万社
実に全企業数の約90%強(全労働人口では全体の約70%)を中小企業が占めている事になる訳です。
では‥‥‥‥‥‥‥冒頭の質問に戻りますが、中小製造業は一体何社あるのでしょう?
上記、中小企業数370万社の内、約50%の200万社に近い中小企業が何らかしかの製造に携わっているとされています。
戦後日本の隆盛はある意味、中小製造企業が支えてきた‥‥‥と言っても過言ではありません。
しかし‥‥‥バブルの崩壊、リーマンショク、アジア諸国の台頭、人口の減少、消費の低迷などから中小製造業の生産は減少傾向にあり、逼迫している状態にあると言えます。
上記全企業では約70%が赤字‥‥中小企業370万社では約80%が赤字‥‥そして中小製造企業においては約90%近い企業が赤字との事です。
この数字を見ると政府が言う好景気感は、甚だ疑問がありますが、一方で国税庁調べによる企業生存率‥‥‥『会社設立後、約90%は10年で倒産‥‥』こちらの方は頷ける感じがします。
然るに、上記データから中小製造企業の置かれている現状は厳しいものがある訳ですが、それを打破し、現在においても黒字成長を続けている中小製造業がある事も事実です。
そんな成長企業には何個かの共通点があります。
まず【危機をどう乗り越えたか?】と言う点での共通点です。
① 若手経営者や後継者が改革を主導・断行
② 社員の意識改革
③ 原点回帰とコア技術の踏襲
④ 選択と集中
これらの具体策を断行し危機を乗り越えています。
また、危機に直面した時、新たな市場や顧客‥‥新たな事業を展開する事で危機を乗り越えた企業も多くあります。
そうした企業に見られるコンピテンシー(行動特性)の共通項は次の通りです。
❶ 戦う領域を絞る
❷ 組み合わせによるバリエーション
❸ サービスやソリューションの提供
❹ プロモーション重視
❺ Io Tへの対応
❻ オープンイノベーション
難しいようですが、❶❷は、今まで1つのプロセスで事業を展開していた場合、少し前後のプロセスを取り入れ、その組み合わせにより戦う領域を変える‥‥‥そうすれば、今まで競合他社が100社あったものが、10社になるかもわかりません。
それがサービスやソリューションとなるのです。
また、自社でそのプロセスが困難な場合、オープンイノベーションとして外部連携を図る‥‥‥‥‥‥あとは、プロモーションにより周知してもらう‥‥‥‥‥このような流れで全体像をイメージすれば難しくはないと思います。
次に【これからの不透明な時代をいかに乗り切るか?】
これにも共通項があります。
製造業において「技術力」「品質」「コスト」重視といったこれまでのモノづくりでは差別化は図れません。
上記は当然の事として、それに加え『サービス』『ソリューション』『圧倒的なスピード』といったソフト面も兼ね備えた【総合力】を高める事‥‥‥‥‥‥
そして、それを広める為の宣伝・広告‥‥いわゆる『プロモーション』を磨く‥現状を打破し、成長している企業はこれらを重要視されています。
最後に製造業の場合、海外生産も重要です。
【海外事業をいかにマネジメントするのか?】

これにも2つ共通点があります。
1. 規則やルールの明確化
2. 現地化
企業を運営する場合、規則やルールを決め順守してもらう‥‥‥これは当たり前の事です。
これにより、業務の効率化が為され、業務も見える化が出来ますので、情報の共有も出来ます。
そして‥‥重要な事は、上記のベースをしっかりと構築した上で、「ローカルはローカルに任せる」‥‥日本で言うところの「郷にいれば郷に従え」‥‥です。
究極は全て現地に任せる「現地化」をしている企業の方が、海外事業は上手く行っているようです。
これから日本の中小製造業を取り巻く環境は益々厳しい曲面を迎える事になると思います。
また、製造業だけではなく、その他の中小企業においても然りです。
上述の「成長企業の共通点」は、全中小企業にとっても大いに参考になると考えますので、是非一考を案じて見てください。
最新の記事
-
2022年09月06日
Vol.6 ディスプレイ広告 -
2022年08月19日
コラムVOL.5 インターネット広告の形式 -
2022年07月27日
コラムVOL.4 WEBマーケティングの集客施策【広告】 -
2022年07月15日
VOL.3 WEBマーケティングの集客施策【広報】 -
2022年06月21日
VOL.2 WEBマーケティングの集客施策 【コンテンツ】 -
2022年06月16日
VOL1.WEBマーケティングを行う理由。 -
2022年05月24日
販促キャンペーンの効果的な方法とは vol.3 -
2022年05月11日
販促キャンペーンの効果的な方法とは vol.2 -
2022年04月27日
販促キャンペーンの効果的な方法とは vol.1 -
2022年04月14日
プロモーション戦略「3C分析」から「5C分析」へ -
2022年03月09日
★2分コラム★ プロモーション戦略でよく耳にする“4P”って?? -
2022年02月26日
紫外線対策は1年中!【UV対策アイテム】を活用しよう -
2022年02月24日
【結婚式場・レストラン・ブライダルジュエリー業界向け】 -
2022年02月09日
大注目の【グラシン紙】ってなに?? -
2022年01月12日
雪や少し先の梅雨の時期【必須】ウォッシャブルアイテム -
2021年12月22日
アウトドアの季節におすすめ!マイカトラリーを持って出かけよう!! -
2021年12月08日
入社式におすすめのノベルティ -
2021年11月24日
海外で人気のグリーティングカードを贈ってみよう! -
2021年11月10日
【塾・予備校・学校向け】ノベルティで受験生を応援しよう! -
2021年10月27日
年末年始のご挨拶やイベントに!
年月アーカイブ
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (3)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (7)
- 2021年4月 (7)
- 2021年3月 (7)
- 2021年2月 (7)
- 2021年1月 (11)
- 2020年12月 (10)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (4)
- 2020年3月 (2)
- 2019年12月 (5)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (5)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (3)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (5)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)

 各種資料ダウンロード
各種資料ダウンロード
 お問い合わせ・無料相談
お問い合わせ・無料相談