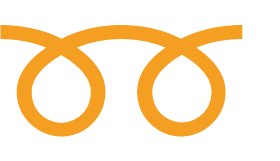2012年07月12日
「人」対「人」
皆さん、こんにちは!
今週、来週位でようやく梅雨明けになりそうな感じですね。
しかし、今回の梅雨は、台風と重なったり、昨日も熊本県では記録的な大雨が降り続いたりということで、多大な被害が出てしまいました。
日々の変化はなかなか、分からない様に、気象の変化も日々では分からないものですが、着実に一昔前とは気候が明らかに異なっていると思います。
私達の日々の仕事においても、その変化は分からないものですが、出来るだけ日々の変化に注視して、少しでも早く、その変化に対応出来る体制を作っておく必要があると考えているところです。
さて、このブログも7月で丸3年になります。
社内メッセージのつもりで綴り始めたものが、廻りの方々の反響がことの他大きく、今ではエジプトでご覧頂いている方もおられると聞きます。
正にマンガの世界が現実になっている感じで、私が子供の頃には考えも及ばなかった訳ですが、その通信・情報のデジタル化・インフラの急速な発展には驚きます。
これは、現代では人との繋がりにおいても、ビジネスの世界においても、不可欠のものとなっています。
このデジタル化・インフラの大きな波は、これからも発展途上国をも飲みこみながら、ますます加速して行くことでしょう。
しかし、人の営みが続く限り、私達はやはりベースには「人」対「人」というアナログ的なやり取りが存在し、そして、そのツールとして利用するというスタンスを忘れてはいけないと思うのです。
このことは社内においても、ことある事に話をします。
そして、人が相手である以上、社内においても、社外においても、場合によっては人生においても、下記の基準値を認識した上で、対峙するようにすれば、よりよい関係を築くことが可能になると考えています。
①期待値
②妥協的期待値
③懸念値
この3つです。②③は私の造語ですが…。
「期待値」というのは、相手がベストだと望んでいる結果を意味します。
社内であれ、お客様であれ、相手から依頼や指示を受けた場合、必ず相手がベストだと望んでいる結果が存在します。
受けた人は、その期待値を上回る答えを出してあげれることが出来れば、信頼され成果に結び着く確率は高くなる訳です。
社内であれ、お客様であれ、的確な依頼や指示をする方は少ないのが普通ですので、受ける側は、まず第一に相手の意図も含めて「期待値」を具体的に抽出することが最重要ポイントとなります。
「妥協的期待値」というのは、相手が『この答えがベストだが、どう考えても不可能に近い。しかし、最低この基準でなくてはならない』という様な判断に乗っ取って、ベストではないがベターだと望んでいる結果 ということです。
受けた人は、この妥協的期待値を100%上回らなければなりません。
何故なら、相手は最低のラインに近いところでの妥協した結果だからです。
そして、妥協的期待値を上回って始めて、土俵に乗るというレベルであることも認識をしておかなくてはなりません。
もう少し言えば、これを下回る結果を出してしまうと、『こんな感じか』と相手の心の中でレッテルを貼られてしまうわけです。
どうしても下回るならば、事前に相手が納得する裏付けを説明して理解を得ておくことが信頼関係においては重要になります。
事務的に作業をしている人、報連相のできない人、変に頑固な人、自分は出来ていると思っている人など、自分の見地の中で仕事をしている様では、まず相手との信頼関係を築くことは出来ませんので、相手の見地に立って、自分は何をしなくてはならないのか?を認識をしなくてはなりません。
この世の中、全て相手が存在しますので、相手の「期待値」や「妥協的期待値」は何なのか?を理解し、それを上回る答えを出せる様に努力をし、答えを出すことで、社内であれ、社外であれ、社会であれ、信頼関係を築いて行くことに繋がるのだと考えています。
また、その逆に自分から相手に依頼や指示をする場合は、上述の様に、自らの「期待値」「妥協的期待値」を社内であれば、同僚や部下、社外であれば購買先に、的確に伝える事を心掛けなければなりません。
この様な「期待値」「妥協的期待値」を皆が認識することで、的確な対応をすることが可能になり、無駄な業務や互いのやり取り、人間関係なども大幅に改善されるという大きな副産物をももたらしてくれる筈です。
最後に「懸念値」ですが、これは仕事においては、ビジネスが始まってから、又は社内においても、社会でも「人」対「人」の付き合いが始まってから、ということになります。
どういうことか言うと、人はまずビジネスの場合でも、社内でも、社会でも、付き合いを始める時、誰でも期待を持って、その人を見ます。
しかし、次第に『そこまでの期待は出来ないなぁ』ということで、その人に対して妥協した見方に変わって行きます。
上述の様に、「妥協的期待値」が相手にとっての最低ラインですので、その空気を理解せず、それを下回る結果を出し続けるとやがて、「懸念値」が誕生してしまいます。
この「懸念値」の発生は、人によって様々です。
私の場合、社内、社外に関わらず、縁あって付き合いが始まった人達と考えていますし、やはり人が大事だと思っていますので、豊臣秀吉ではないですが、「鳴かぬなら、鳴かせてみようホトトギス」という感じで、社内では出来るだけ居場所を作ってあげながら、社外においても成長させながら、しつこく諦めないで育成することを心掛けています。
しかし、お客様や時代の「懸念値」は、そんな悠長なことを許してくれないということは、肝に据えて置かなくてはならないのです。
恐らく、1~2回の「商品」や「人」の品質不良で「懸念値」となり、次に同じ様な失態が発生すると、信頼は失墜し、取り引きはなくなるでしょう。
社内で言えば重要な事案を任されることはなくなるということを意味するのです。
今日お話ししたことは、ビジネスや社会において、信頼される人というところでの1つのコツです。
自分の見地だけで物事を計るのではなく、相手の立場に立って、その「期待値」「妥協的期待値」そして「懸念値」を認識し、対応して行かれれば、仕事においても、人生においても、素晴らしい結果がついてくるのではないか?と思います。
どうぞ、参考になさって下さい。
ちなみに、私と家内の場合、上述に乗っ取って話をすると、私から見て家内は「期待値」に近いところ、家内から見て私は「妥協的期待値」というところから、土俵に乗り、付き合いが始まったと思います。
そして、付き合い始めてから、今日まで、約30年が過ぎましたが、それなりの「懸念値」もありましたが、それを下回り続けることがなく、今もそしてこれからも続いて行くというところでしょうか。
社内においても、社外においても、永く繋がる信頼関係を構築して行きたいものですね。
最新の記事
-
2018年07月06日
働き方改革 PART2 -
2018年06月22日
考え方プラス?マイナス? -
2018年06月08日
働き方改革⁈ -
2018年05月25日
振り返り……⁈ -
2018年04月13日
脈々と…… -
2018年04月06日
リーダーに必要な5つの資質⁈ -
2018年03月23日
ドラッカー 5つの質問⁉︎ -
2018年03月16日
ドラッカー流 時間管理術 -
2018年03月09日
ラクして速く成果を挙げる⁉︎ -
2018年02月23日
チームとしての部下育成 -
2018年02月09日
強くなるアマチュアスポーツの理由⁈ -
2018年01月27日
課題と問題の違い?? -
2018年01月12日
新春 決意‼︎ -
2017年12月22日
2018年 捨てる→進化→継続成長 ⁉︎ -
2017年12月08日
個と組織の力を伸ばす‼︎ -
2017年11月24日
飽くなきチャレンジ‼︎
年月アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (3)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (4)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (5)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (5)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (3)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (5)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (4)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (5)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (5)
- 2013年10月 (4)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (5)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (4)
- 2013年3月 (5)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (5)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (5)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (4)
- 2011年7月 (5)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (4)
- 2011年4月 (5)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (4)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (4)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (5)
- 2010年9月 (5)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (5)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (4)
- 2010年4月 (5)
- 2010年3月 (4)
- 2010年2月 (4)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (4)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (4)
- 2009年8月 (4)
- 2009年7月 (5)
- 2009年6月 (4)
- 2009年5月 (5)
- 2009年4月 (4)
- 2009年3月 (3)
- 2009年2月 (2)
- 2009年1月 (3)
- 2008年12月 (3)
- 2008年11月 (2)
- 2008年10月 (3)
- 2008年9月 (3)
- 2008年8月 (3)
- 2008年7月 (2)

 各種資料ダウンロード
各種資料ダウンロード
 お問い合わせ・無料相談
お問い合わせ・無料相談