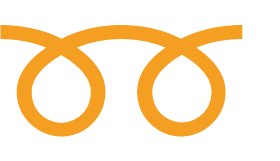2015年10月02日
素敵な魔法
皆さん、こんにちは‼︎
もはや10月ですね。
随分と涼しくなって来ました。
道行く人達の服装も秋らしくなりました。
この10月から会社ではネクタイ着用という事で、久しぶりにネクタイをしました。
元来ネクタイはあまり好きではないので、何か違和感がありますが、ネクタイを締める事によって気が引き締まる‥‥そんな感じもします。
さぁ〜今年も残すところ、あと3ヶ月、気合いを入れ直すとしますか‼︎
さて‥‥‥私達の会社は大阪、奈良を拠点として、東京に営業所があり、中国にも工場があります。
私の家族は東京におり、また仕事の関係もありますので、大阪ー東京を月に数回、行き来しています。
もうかれこれ、この様な生活を18年間続けています。
若い時はまだしも、歳を重ねて来ますと、段々とそれもしんどくなって来ている現状はありますが‥‥‥‥‥。
まぁ〜そんな事は言えませんので、ムチ打って頑張っています。
移動は新幹線ですが、昨日も移動の新幹線で備え置きの雑誌を読んでいました。
その中に「伸びている会社」の特集記事がありましたので、今日は印象に残っている記事をご紹介したいと思います。
これは大手食品メーカーの記事です。
その中で印象に残っているワードは2つ!
1つは「残業ゼロから意識改革が始まる」という言葉です。
その会社は大手メーカーでは珍しく残業はゼロだそうです。
ラインによっては3部制を布いてはいるものの人に対する残業は無いとの事でした。
メーカーの場合、生産と結果が比例しますので、本来、生産時間が決められてしまうと、自ずと結果も決ってしまい、それ以上の業績の向上は難しいものです。
しかし、そのメーカーは毎年順調に業績を伸ばされていると言います。
何故でしょう?
答えは至ってシンプルです。
各々が任せられたポジションで、常に効率改善を実行しているからです。
「残業をゼロ」にする事により、自ずと退社時間が決められてしまいます。
そしてその時間内で行わなければならない仕事や業務があります。
生産の場合、そこに携わる人達は、「今まで1時間に100個生産していたものを、1時間に120個生産出来ないものか?」と考える様になります。
残業が当たり前の意識では考えが及ばない事です。
残業をゼロにする事で、その様な意識付けをされているのだと考えます。
限られた時間で生産を上げるには?
限られた時間で営業成績を上げるには?
限られた時間で業務を終わらせるには?
限られた時間で出荷を終わらせるには?
‥‥‥‥という様に、時間が決められてしまう事によって、各々が任されたポジション‥‥取り分けその職場のトップは考えざるを得ません。
それにより、生産効率や営業効率、業務効率、出荷効率などが改善され、余剰人員を抱えなくても済み、原価ベースが下がり、あとは営業が時間内(決められた期限)までに、自分達の目標をクリアしてくれれば、自然と業績は向上するという事なのです。
こと細かく言う事は大事です。
しかし、上位者もベッタリとくっついて仕事をしている訳ではありませんので、全てをチェックして改善する事は不可能です。
それぞれの仕事や業務に携わる人達が、意識を高く持ちそれを実行、実現して行く事‥‥‥これが一番望ましいし、理想の「あるべき姿」なのです。
その為には‥‥「残業はゼロ‥‥そしてその時間内で結果を出せ‼︎」と社長も去る事ながら、チームリーダーである管理職の人達が率先して言動しなければならないと言います。
実行部隊の長である人達が変わらなければ、幾ら社長が叫んだところで全体の意識は変わらないと‥‥。
逆に言えば社長の立場からして‥‥上記を基にして考えると、誰をチームリーダーにするのか?が、自身の描いた経営目標を具現化する上では、一番大事であるとも言われています。
そしてもう1つ、心に残っているワードとして「頑張るな」という言葉です。
その大手食品メーカーの社長は、社員達に「残業はゼロ‥‥そして頑張るな」とよく言われていると言います。
その真意はどこにあるのでしょう?
記事を読んで行くうちに「そう言う事かぁ」と納得しました。
現社長が就任した当時、会社業績は芳しく無い状況だったそうです。
そこで、まず現状把握をすべく、各部署のリーダー達との意見交換に時間を費やしたと言います。
そこでその社長が感じた事は、どの部署においても、結果を生み出す仕事や業務の効率が悪く、無駄が多いと分かったと言います。
「これらを改善すれば業績は必ず回復する‥‥」この様に思われたそうです。
しかし、チームリーダーが話の最後に言われる事は、決まって「皆んな頑張っています」と言う言葉だったと言います。
この言葉に社長は危機感を持ったそうです。
「無駄を無くしそれぞれの部署が効率改善を行えば、必ず結果は出るはずだ‥‥‥しかし、それを率先して引っ張って行ってもらわなくてはならないチームリーダーがこれでは何も変わらない」と思われたそうです。
それ以降、社長は特にチームリーダー達に対して「頑張らなくても結構です。ただ結果を出して下さい!そして残業をゼロにして下さい!」と言い続けたそうです。
これが、「頑張るな」の真意です。
頑張って結果が出ない‥‥‥のであれば効率とは呼びません。
頑張って少なからず結果が伴うから効率というものが発生するのです。
頑張らずに結果を出す‥‥‥究極の効率を目指しなさいということだと思います。
例えば、生産現場の場合、仕事が立て込んで来ると現場責任者の方は、「今日から1週間残業!」という形で生産を間に合わせてくれていました。
確かに、突発的な対処、応急処置として、皆さん遅くまで残業をして間に合わせてくれる‥‥‥有難い事ですしホント助かります。
しかし一方で、万事この様な対処で生産をしていると当然ながら原価ベースが上がり、利益率を押し下げる事に繋がってしまいます。
「同じ時間で生産量を上げる‥‥」こうすると、生産効率がよくなりますので、原価ベースは下がり、利益率はアップします。
如何に付加価値を付け‥‥‥または効率を上げ、利益率を高める事が出来るのか‥‥‥これを企業は追求して行かなくてはなりませんし、利益率の飽くなき改善こそ、企業業績を押し上げて行く重要なファクターなのです。
生産現場を例に上げましたが、営業でも‥‥‥どの部署でも同様です。
営業であれば、「同じ時間以下で昨年以上の結果を出すには‥‥」「同じ人数以下で昨年以上の結果を出すには‥‥」こんな事を常にチームリーダーは考え実行し結果を出して行かなければならないという事です。
逆を言えば「昨年より、同じ時間や人数以上に費やしているのに結果は昨年以下‥‥」こんな事も時代が変化し、日々時間に追われる中でよくある事ではないでしょうか?
今までと同じ様に行動していても売上が下がる‥‥‥他に手が回らないから、残業をする‥‥または人を入れる‥‥‥これでは烏合の衆と化すだけで業績はどんどん悪化の方へ行ってしまっているのです。
現代においては、どのポジションにおいても、特にそのチームリーダーは現状効率はどうなっているのか?を把握して効率改善を常にしなくてはなりません。
「残業はゼロ‥」
「頑張らなくても結構‥結果を出しなさい」
この2つのワードを繰り返えす中で、少しずつ意識改善が見られる様になり、少しずつ効率も高まり業績も少しずつ回復して行ったと言います。
そして、劇的な変化は就任2年目、自ら営業課長に抜擢した人物が率いる営業部署が、前期比を6ヶ月前倒しでクリアし、目標を大きく上回ったそうです。
そうなると周りの部署責任者達も俄かに焦り出し、以前は「傷の舐め合い」「ドングリの背比べ」‥‥言い訳のオンパレードだったものが「切磋琢磨」する様になり、我先に効率改善の話しを互いがし、社内雰囲気もよくなり、建設的な意見が往来する様になったと言われています。
「本来、仕事としては、そっちの方がしんどいはずやけど、皆生き生きして取り組む様になって来た」‥‥‥と。
それ以降、業績は順調そのものだと言う事でした。
その社長は「残業ゼロ」「頑張らず結果を出す」‥‥この2つのワードは魔法の言葉と言われています。
社長も‥‥そしてチームリーダーも社員達に魔法をかけましょう‼︎
最後にもう1つ。
上述の2つのワードは意識を変える魔法の言葉でした。
それにより「気づき」を与え、意識改革をしてもらい、自ら行動をする‥‥この様な善の循環にして欲しい為のものです。
もう1つはやはり目標管理です。
意識が変わり、行動が変わっても、やはり私達は期限までに結果を残さなくてはなりません。
その為には、社長も去る事ながら各チームリーダーの目標意識と目標管理が重要であると言われています。
その会社の目標管理のポイントは5つです。
①まず経営目標が社長より提示されます。
②そして部署に振り分けられます。
③その中でまずチームリーダーは一番高い目標設定をします。
④あとは部下達に振り分けます。(ただし、前期比以上)
⑤そして各々の裏付けと成し得る為の活動計画をチームで作成。
これだけです。
極々当たり前ですし、シンプルです。
あとはPDCAを回しながら、月1度の進捗管理を行う‥‥‥これだけです。
前者社長は、意識改革と目標管理が重要と言われていますが、意識改革が伴わない時には、中々目標管理もままならなかったと言います。
今は意識改革も出来たので、目標管理は当たり前の手法として、チームリーダーが行ってくれていると‥‥‥。
こう考えると、「気づき」→「意識改革」が何よりも重要で、チームリーダーの言動がチームの浮沈を担っている‥‥こんな事です。
皆さんも是非、素敵な魔法にかかってみては如何ですか?
最新の記事
-
2018年07月06日
働き方改革 PART2 -
2018年06月22日
考え方プラス?マイナス? -
2018年06月08日
働き方改革⁈ -
2018年05月25日
振り返り……⁈ -
2018年04月13日
脈々と…… -
2018年04月06日
リーダーに必要な5つの資質⁈ -
2018年03月23日
ドラッカー 5つの質問⁉︎ -
2018年03月16日
ドラッカー流 時間管理術 -
2018年03月09日
ラクして速く成果を挙げる⁉︎ -
2018年02月23日
チームとしての部下育成 -
2018年02月09日
強くなるアマチュアスポーツの理由⁈ -
2018年01月27日
課題と問題の違い?? -
2018年01月12日
新春 決意‼︎ -
2017年12月22日
2018年 捨てる→進化→継続成長 ⁉︎ -
2017年12月08日
個と組織の力を伸ばす‼︎ -
2017年11月24日
飽くなきチャレンジ‼︎
年月アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (3)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (4)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (5)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (5)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (3)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (5)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (4)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (5)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (5)
- 2013年10月 (4)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (5)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (4)
- 2013年3月 (5)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (5)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (5)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (4)
- 2011年7月 (5)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (4)
- 2011年4月 (5)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (4)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (4)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (5)
- 2010年9月 (5)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (5)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (4)
- 2010年4月 (5)
- 2010年3月 (4)
- 2010年2月 (4)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (4)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (4)
- 2009年8月 (4)
- 2009年7月 (5)
- 2009年6月 (4)
- 2009年5月 (5)
- 2009年4月 (4)
- 2009年3月 (3)
- 2009年2月 (2)
- 2009年1月 (3)
- 2008年12月 (3)
- 2008年11月 (2)
- 2008年10月 (3)
- 2008年9月 (3)
- 2008年8月 (3)
- 2008年7月 (2)

 各種資料ダウンロード
各種資料ダウンロード
 お問い合わせ・無料相談
お問い合わせ・無料相談