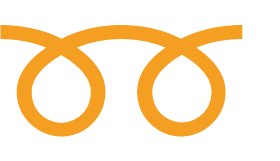2016年09月30日
平均IQ120以上⁈
皆さん、こんにちは‼
今週もすっきりとした天気ではなかったですね。
9月に入ってから、晴れ間は殆ど数えるぐらいしかなかったのではないでしょうか?
ちょっと異常な感じがします‥‥‥‥
これだけ長く天気が悪いと消費にも悪影響を及ぼしかねません。
来週も予報によりますと、愚図ついた天気が続くそうです。
行楽シーズンの10月でもありますので、天候の方も早く回復してもらいものですね。
さて‥‥ところで皆さん、園児のほぼ全員がIQ120超を誇る幼稚園があるのをご存知でしょうか?
その幼稚園は「東京いずみ幼稚園」と言います。
人を教える‥‥人を育てる‥‥という事は並大抵の事ではありません。
学校であっても、企業であっても、教育・育成は永遠のテーマです。
特に企業は「人は金なり」と言われるように、企業成長には、人の成長は欠かす事が出来ません。
人財に対する教育・育成システムがあり、そして全員がある一定期間までに、ある一定の基準以上に育ってくれる‥‥‥‥言わば全員が80点以上の成績で、その中から90点100点を取る人達が現れてくれる‥‥‥‥‥これが理想であろうと思います。
しかし、現実は学校であれ、企業であれ、30点の人もいれば、50点70点100点の人も存在する‥‥‥‥‥バラバラです。
学校で言えば、勉強を自らする人は100点近い点数を取り、そうでない人は点数が低い‥‥‥‥企業で言えば仕事意識の高い人は100点近い点数を取り、そうでない人は点数が低い‥‥‥‥‥乱暴な言い方をすれば、こういう事です。
実際のところ、こういう事であれば、これは最早、それぞれの人の資質・意識によるところ‥‥‥という事になってしまいます。
これでは教育・育成とは呼べませんね。
上述の幼稚園は、何も優秀な子たちのみが入るエリート幼稚園ではありません。
極々一般の幼稚園で、園児達もその地域に住まわれている下町育ちのお子さん達ばかりだそうです。
言わば、人の資質ではなく、教育の方法によって、IQの凸凹をなくし、ほぼ全員の園児達をIQ120以上にしているというから驚きです。
では‥‥‥‥どのような方法で教育を行っているのでしょう?
例えば国語の場合、教育学博士の石井勲さんが提唱する「石井式国語教育」を取り入れ、漢字に力を入れられています。
石井式国語教育のコンセプトは、幼児にとって、漢字はカナより易しい‥‥‥というもので、漢字は平仮名よりも直線が多い為、幼児達には絵を見るのと同じように認識されるという事です。
従って、まず単語や熟語をカードに記して子ども達に見せ、絵として認識をさせます。
次に「論語」「源氏物語」「百人一首」などを題材に、文脈の中で漢字の形や意味を覚えさせるそうです。
文脈や漢字の意味を学ぶ事で、思考力や理解力の土台になると言われています。
やはり文脈を理解する‥‥ただ読むだけではなく、意味を理解しながら文章を読む‥‥という事は大事なんですね。
スキルの高い人に読書家が多いのが頷けます。
こんな事から「東京いずみ幼稚園」では、当たり前のように、教室の掲示板は全て漢字‥‥‥子ども達のスモックや体操服についている名札も全て漢字で書かれているそうです。
算数においても九九を取り入れていて、園児達のほぼ全員が出来るとの事です。
国語、算数において共通する事は、まず視覚に訴える‥‥‥次に言葉を用いて聴覚に訴えかけ伝える‥‥‥そして、例えば2×9は何故18になるのか?のように、国語も算数も丸暗記をさせるのではなく考えさせる‥‥‥‥このような教育方法です。
視覚と聴覚で‥‥‥これは私達も様々な場面で「伝える」という事をしなくてはならない訳ですが、より相手に理解をしてもらう時、応用が利く感じがします。
他に、園児達全員がIQ120以上という事だけではなく、ほぼ全員が絶対音感を持っていると言います。
この絶対音感も私達の認識は、持って生まれた特殊な才能‥‥‥‥と考えているのではないでしょうか?
従って教育だけでは、どうにもならない‥‥‥‥‥まず才能が無いと‥‥‥‥と思っています。
しかし、東京いずみ幼稚園では「ミュージックステップ」という教育方法で、全員に絶対音感を身に付けさせています。
その方法は、園児達にアイマスクを装着させ、先生が弾いたピアノの音を「ド」は膝に手を‥‥「レ」は腰に手を‥‥といったように、音1つ1つに対して決まったポーズを連続して答えていきます。
目を瞑らせると、目を瞑る事に集中してしまうので駄目だそうです。
アイマスクをする事で聴覚がより研ぎ澄まされるという訳です。
これを繰り返す事で、ほぼ全員の園児達は絶対音感を身に付けるのだそうです。
また、昨今、身体能力の低下が言われていますが、「東京いずみ幼稚園」では、毎朝2分、相撲の四股をするそうです。
足腰を鍛える事で身体能力や走力が見違えるように改善されたという事です。
これ以外でも独自の教育方法に基づき、園児達の成長を後押しされています。
当初、このような教育方法は幼稚園児からすると行き過ぎとの批判が親御さん達からあったそうですが、暫くすると園児達の成長が目に見える形で現れ、今では親御さん達も全面バックアップしているのだそうです。
こう考えると改めて教育の重要性を思い知らされます。
企業としても、誰であれ、ある一定期間までに平均80点以上へと全員が成長出来る‥‥‥それを全社でバックアップしてあげる‥‥‥そんな教育・育成方法を作れないものか?
そんな事が可能ではないか?
改めて考えさせられる今日この頃です。
最新の記事
-
2018年07月06日
働き方改革 PART2 -
2018年06月22日
考え方プラス?マイナス? -
2018年06月08日
働き方改革⁈ -
2018年05月25日
振り返り……⁈ -
2018年04月13日
脈々と…… -
2018年04月06日
リーダーに必要な5つの資質⁈ -
2018年03月23日
ドラッカー 5つの質問⁉︎ -
2018年03月16日
ドラッカー流 時間管理術 -
2018年03月09日
ラクして速く成果を挙げる⁉︎ -
2018年02月23日
チームとしての部下育成 -
2018年02月09日
強くなるアマチュアスポーツの理由⁈ -
2018年01月27日
課題と問題の違い?? -
2018年01月12日
新春 決意‼︎ -
2017年12月22日
2018年 捨てる→進化→継続成長 ⁉︎ -
2017年12月08日
個と組織の力を伸ばす‼︎ -
2017年11月24日
飽くなきチャレンジ‼︎
年月アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (3)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (4)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (5)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (5)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (3)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (5)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (4)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (5)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (5)
- 2013年10月 (4)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (5)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (4)
- 2013年3月 (5)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (5)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (5)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (4)
- 2011年7月 (5)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (4)
- 2011年4月 (5)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (4)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (4)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (5)
- 2010年9月 (5)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (5)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (4)
- 2010年4月 (5)
- 2010年3月 (4)
- 2010年2月 (4)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (4)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (4)
- 2009年8月 (4)
- 2009年7月 (5)
- 2009年6月 (4)
- 2009年5月 (5)
- 2009年4月 (4)
- 2009年3月 (3)
- 2009年2月 (2)
- 2009年1月 (3)
- 2008年12月 (3)
- 2008年11月 (2)
- 2008年10月 (3)
- 2008年9月 (3)
- 2008年8月 (3)
- 2008年7月 (2)

 各種資料ダウンロード
各種資料ダウンロード
 お問い合わせ・無料相談
お問い合わせ・無料相談