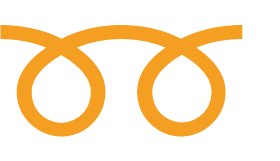2017年10月20日
成長メカニズム
皆さん、こんにちは‼︎
めっきり涼しくなって来ました。
それにここ1週間から10日ぐらい、昔の梅雨のようにシトシトと雨が降り続いています。
この時期にこれだけ冷えるのも……雨が降り続くのも珍しいのではないでしょうか?
例年以上に気温の変化が激しい感じです。
どうぞお身体をご自愛ください。
さて、話は変わりますが、
「成長メカニズム」
という言葉をご存知でしょうか?
会社の成長は、
そこで働くスタッフ1人1人の成長無しにはありえません。
その成長を促進させる方法があると言う訳です。
以前…私達が若い頃は以下のようなメカニズムでした。
① 知識や考え方
其々の職務における知識や考え方を、上司からのレクチャーを受けます。
② 行動
③ 成果
私は大学を卒業後、商社に入社し、営業職に付きました。
上述のように、営業としてのマナーや最低限の知識のレクチャーを
1週間程度受け、数十社の顧客データを渡され、
「明日から実践な…1日の粗利益ノルマはこれだけ…」
こんな感じのスタートでした。
その商社は毎朝、1人1人ノルマ報告があり、ノルマが達成されないと、酷い叱責や嫌味を浴びせられます。
当然入社して1週間の人間が、
直ぐに売上・利益を上げられる訳もありません。
既存顧客からは、しばしば既存商品の注文は入っていましたが、
それだけを処理していたのでは売上・利益ノルマに到達する訳もなく、1ケ月ぐらいはノルマ未達が続きました。
その間、毎朝の叱責が続き、針のむしろ状態の中、自分なりに様々な提案方法を考え、試行錯誤しながら行動をしていました。
ようやく1ケ月が経ち、最低限のノルマはクリア出来るようになりました。
すると、翌月から倍のノルマを課せられます……
また、自身で試行錯誤しながら既存深耕・新規開拓をし、そのノルマをクリアして行きます………
昔は先輩のやり方を盗んで、自分自身で考えてやりなさい…………このようなやり方が多かったのだと思います。
しかし、これでは属人化してしまい、個々のスキルに頼る事になり、会社としての基準がなく、気が付けば3年間、入社する人みんな辞めていました。
その頃から、上述のメカニズムでは機能をしなくなって来ていたのかもしれません。
そんな中、新たな「成長メカニズム」が生まれました。
個々の成長を速やかなにし全体最適を作り出すメカニズムです。
① 知識や考え方
② 能力(スキル)
③ 行動
④ 成果
このようなメカニズムです。
変化したところは「能力」です。
以前のメカニズムでは、その「能力」の部分がその人任せでした。
知識や考え方だけを教えて
「さぁ〜やりなさい」
「行動をしなさい」
と言われても、やる気はあってもどのようにして行えば良いのか?が分からず、結果、個々のスキルに頼る事になり、属人化してしまい、成果もまばらで時間も要する事になっていたのです。
そこで考えられたのが「能力」というメカニズムです。
能力は「手順書」×「技能」で現す事が出来ます。
手順書は、
よりよい仕事を効率的に進める為のマニュアルです。
技能とは、手順書を繰り返しの行う事で身に付くものです。
ロープレも技能UPの手段として有効です。
例えば新規営業の場合、
どのような企業リサーチを行い、どのようなトークスクリプトでアプローチをするのか?
そして、商談時にはどのようにプレゼンを行い、どのような情報を顧客から聞くのか?
このような内容を単に教えるだけではなく、具体的に手順書として落とし込み、フォーマットを作成し、行動に移せるようにしてあげる………
これがメカニズムで言うところの「能力」です。
このメカニズムを挟む事で、属人化を防ぎ、時間のロスを防ぎ、成果のバラツキを防ぎ、全員がある一定の基準のスキルを持って行動する事が可能になり、行動の標準化、全体最適が実現し、営業全体のレベルアップに繋がります。
これは生産や業務、出荷などあらゆる部門部署においても同じ事です。
例えば弊社生産においての手順書は
図面作成→治具作成→生産→工程内検査……
この手順を踏む事で効率良く品質の安定した生産を生み出す事が可能になり、機械のオペーレーション(How To)が出来れば、ほぼ誰が生産しても成果物は同じものになります。
手順書を作成する……
ロープレをする……
決まった手順書をきっちりと遵守させる………
これらは部下達が速やかに成長する為にも、また、自身が少しでも楽になる為にも、上司としては心掛け実行をして行かねばなりません。
手順書というチーム内での叩き台・共通認識があるので、更に能力アップを目指す時、チーム内で議論をし、手順書のブラシュアップをするだけで良いのです。
これが現代のリーダーが部下育成に際してのあるべき姿と方法論となります。
1人が成長してくれる事は非常に有り難い事ではありますし、どのチームにもリーダーは必要です。
しかし1人では出来る範囲に限界があります。
従って属人化せず、チームとして全員が1歩成長する……………
このような会社、チームを作って行かなければなりません。
その為には、「どのように……」という部分において手順書まで落とし込み、ロープレやOJTなどを用いて上司は指導・教育をしてあげる……それにより人は成長するのです。
ISOもまた、手順書、フォーマット、記録→改善……この実行を
五月蝿く言っています。
取得されている会社であれば、このような概念や仕組みはあるのではないかと思います。
成長とは「当たり前の基準が上がる事」……
これが出来れば更にまた同じようなメカニズムを用いて1歩上の基準を目指す……………
この繰り返しを行う事でチーム力というものは、どんどん向上して行くものなのです。
成長メカニズム……
「能力」は「手順書」×「技能」……
教えた事に対して…または、目指す成果物に対して、
『どのようにすれば成し得るのか?』を手順書まで落とし込み、実際の行動に移せる状態にまでしてあげ、そしてそれを検証し、再び指導や教育、はたまた改善を行い、チームを向上させる……………
今のリーダー達はこのメカニズムを上手く活用し全体最適を作り出し、部下達を成長させてください。
最新の記事
-
2018年07月06日
働き方改革 PART2 -
2018年06月22日
考え方プラス?マイナス? -
2018年06月08日
働き方改革⁈ -
2018年05月25日
振り返り……⁈ -
2018年04月13日
脈々と…… -
2018年04月06日
リーダーに必要な5つの資質⁈ -
2018年03月23日
ドラッカー 5つの質問⁉︎ -
2018年03月16日
ドラッカー流 時間管理術 -
2018年03月09日
ラクして速く成果を挙げる⁉︎ -
2018年02月23日
チームとしての部下育成 -
2018年02月09日
強くなるアマチュアスポーツの理由⁈ -
2018年01月27日
課題と問題の違い?? -
2018年01月12日
新春 決意‼︎ -
2017年12月22日
2018年 捨てる→進化→継続成長 ⁉︎ -
2017年12月08日
個と組織の力を伸ばす‼︎ -
2017年11月24日
飽くなきチャレンジ‼︎
年月アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (3)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (4)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (5)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (5)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (3)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (5)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (4)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (5)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (5)
- 2013年10月 (4)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (5)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (4)
- 2013年3月 (5)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (5)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (5)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (4)
- 2011年7月 (5)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (4)
- 2011年4月 (5)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (4)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (4)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (5)
- 2010年9月 (5)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (5)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (4)
- 2010年4月 (5)
- 2010年3月 (4)
- 2010年2月 (4)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (4)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (4)
- 2009年8月 (4)
- 2009年7月 (5)
- 2009年6月 (4)
- 2009年5月 (5)
- 2009年4月 (4)
- 2009年3月 (3)
- 2009年2月 (2)
- 2009年1月 (3)
- 2008年12月 (3)
- 2008年11月 (2)
- 2008年10月 (3)
- 2008年9月 (3)
- 2008年8月 (3)
- 2008年7月 (2)

 各種資料ダウンロード
各種資料ダウンロード
 お問い合わせ・無料相談
お問い合わせ・無料相談